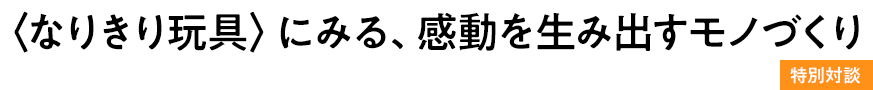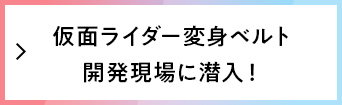〈なりきり玩具〉は“想い出再生機”
——岡本さんはモノづくりがお好きで、大学では橋や線路など社会基盤の設計を勉強していらっしゃいます。モノづくりを始めたきっかけは何だったのでしょうか?

小さい頃は科学者になりたいと思っていたんですけど……。

すごいですね。何がきっかけですか?

宇宙や自然現象に素朴に憧れていたんですが、だんだん人の生活に直接届くようなモノに関心が移ってきて、インフラ系のモノづくりの勉強をするようになりました。いま私が取り組んでいるのは、公共事業の技術が多いのですが、おもちゃも福祉という社会性がありますよね?

そうですね。たとえば岡本さんに影響を与えたと伺った『仮面ライダーオーズ/OOO』は、「昆虫メダルをそろえよう」とか「鳥類のメダルを集めるといいことあるよ」とか、自然に動物図鑑遊びができるしくみになっています。子どもが好きなように遊んでいるうちに「タカ! トラ! バッタ!」を覚えたり(笑)。すべてのライダーがそうではないのですが、「英語を覚えよう」「数字を学ぼう」と子どもに思ってもらえるといいなという裏テーマがあったりします。もともとベースとして『仮面ライダー』は、「孤高のヒーロー」を描いていて、「責任」や「使命」を背負って戦うことがテーマになっています。
バンダイの〈なりきり玩具〉のいいところは、「モノにコトをのっけられる」。公共性やメッセージを作品とシンクロさせることでおもちゃにのせられるんです。


——岡本さんは、ライダーベルトを着けて受験勉強をされていたとのことですが。

小さい頃から、コスチュームを着たり、ごっこ遊びをしたりすることが好きだったので、その延長でやってました。

それはいいことですね。たとえば『仮面ライダーギーツ』という番組がなかったとして、ギミック玩具として変身ベルトを販売していても魅力は伝わらず売れないと思います。僕たちは〈なりきり玩具〉を“想い出再生機”と呼んでいるのですが、「仮面ライダーがピンチを脱した」「困難を乗り越えた」というシーンを子どもたちは変身ベルトを通じて思い出すから、岡本さんも受験勉強で変身ベルトをまくことで「自分もできる!」と思えたんでしょうね。おもちゃのギミックだけでなく、シーンを思い浮かべられることが価値として乗っかっている。そこを〈なりきり玩具〉では一番大切にしています。